くるくる保健室No .20『━血管事故を防ぐ生活習慣━アンチエイジングは血管力が決め手!!』
- くるくるチャンネル事務局
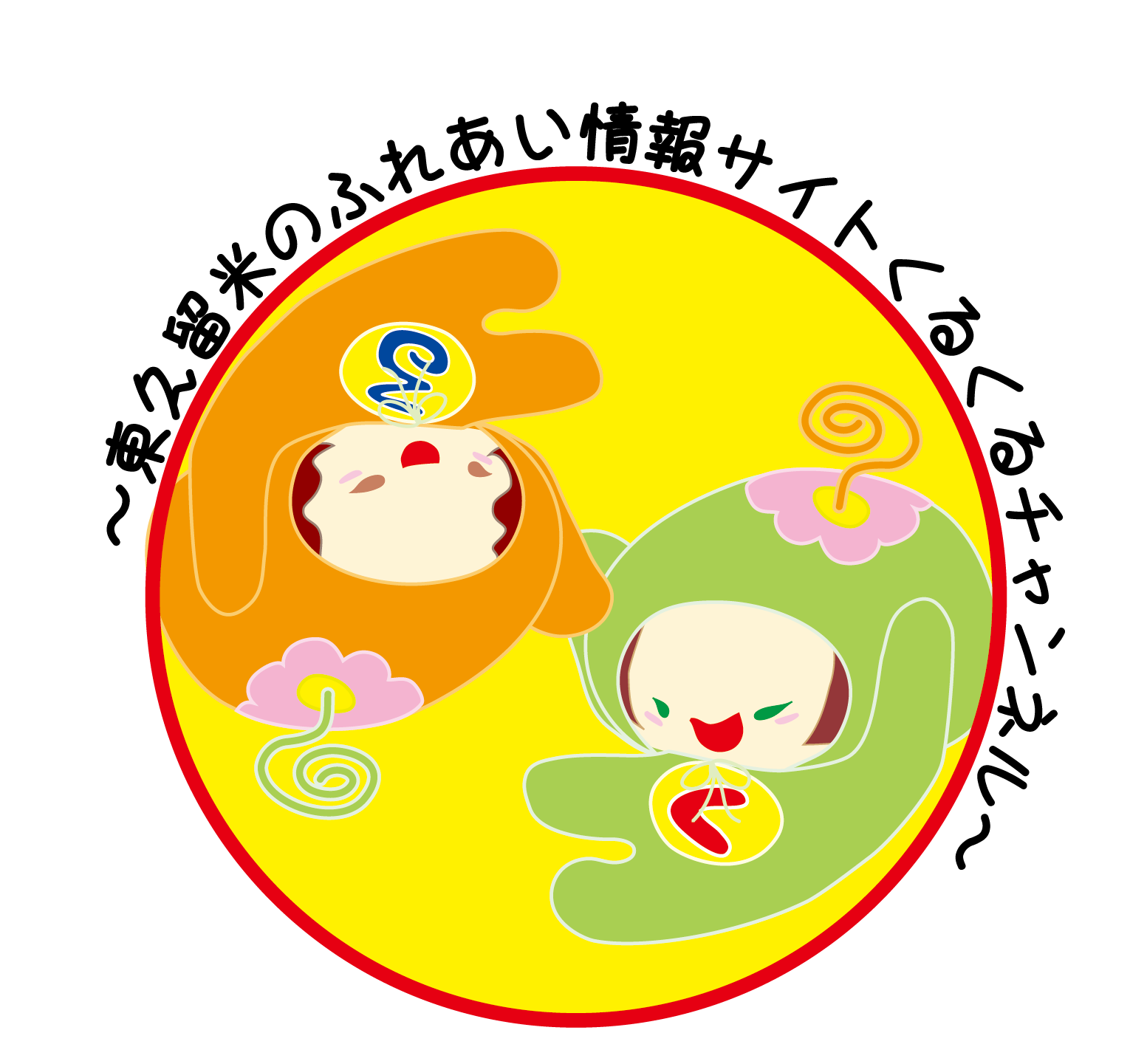
- 2018年2月19日
- 読了時間: 18分

季節が寒くなるにつれて、最近『血管事故』に気を付けましょう!というPRを各メディアがこぞって行ないますが、血管事故とは一体なんぞや?と疑問に思われる方は少なくないはずです。今回のくるくる保健室では血管事故を予防する生活習慣や健康寿命を伸ばし若返りまで可能にしてくれるという血管についてお話ししたいと思います。
皆さん!我々の体の中を張り巡らしている血管の総長さは一体どれくらいだと思いますか?なんと約10万㎞にも及び、地球を2周半もする人体最大の臓器と言っても過言ではありません。血管の中を流れ、体内の60兆個の細胞一つひとつに栄養や酸素、ホルモン等を届けてくれるのが血液という訳ですが、その血液の流れ(血流)が悪くなると色々な病気が発症する訳です。血流の状態が良いのか悪いのかを判断するのに決定的なのが血管そのものなのです。では、血管の状態をどうすればいいのでしょうか?血流をサラサラにさせるだけでは冒頭の『血管事故』を防ぐには不十分です。キーワードはなめらかでしなやかなな血管を養うことが重要です。
それでは、ここからは血管の老化がなぜ起きて動脈硬化が発症してしまうのかを探って参りましょう! 血管は基本的には動脈も静脈も内膜・中膜・外膜という3層構造で成り立っております。 外膜は血管を外部から保護する役割を担っており一番外側にある膜です。中膜は血圧に合わせて収縮し、血管に掛かる圧力を受け止めており、弾力性のある繊維でできています。内膜は血管の柔らかさを保つ物質を分泌し、血管の収縮・拡張の調整、血液を凝固しにくくするなどの働きがあります。そして動脈硬化との関係において非常に重要な役割を果たしている血管内皮細胞で覆われております。この血管内皮細胞の働きは非常に重要で先ずは血管と血液を分け、血液が外に漏れないようにしています。そして活性酸素から血管を守って、血小板が凝固するのを防ぎ血管の炎症を抑制しています。血管の壁を柔軟に保ったり、収縮・拡張をコントロールして、動脈硬化を予防しています。 血管の老化は、血液と接する血管内皮細胞に悪玉コレステロール(LDL)が入り込むところから始まり、入り込んだ悪玉コレステロールはプラークという粥状の塊を形成します。このプラークの破裂とそれに続く血栓の形成が、心筋梗塞や脳卒中の引き金となるのです。ただし、このプラークの中にも、破裂しやすいまさに小籠包の様な不安定なプラークと、肉まんの様に破れにくい安定したプラークがあります。もし、プラークが出来てしまっても、生活習慣を改善しさえすれば血管内皮細胞が生まれ変わり、表面を丈夫な皮膜で覆い安定プラークへと変化させる事ができます。血管事故を発生させないためには、いかにプラークを安定させ、皮膜の強い破れない肉まんを作ることが重要になります。
次に安定プラークを作る生活習慣を栄養面と運動面からアプローチしたいと想いますが、ちょっとその前に皆様にご自身の血管年齢をチェックして頂きましょう!
□階段をのぼると胸がしめつけられることがある □インスタント食品や脂っこい食事を好んで食べる □電話が鳴ったらすぐ取らないとイヤだ □責任感が強く、仕事や家事で手を抜けない □いつも時間に追われている感覚がある □1日の喫煙本数×喫煙年数が400本以上になる □血圧が高い □運動不足だ □物忘れをよくする □手足が冷たく、しびれを感じる □コレステロール値、または血糖値が高い □親、または兄弟に心筋梗塞や脳卒中で倒れた人がいる 上の質問事項に当てはまる数があなたの予想血管年齢です!何個付きましたか? 0~4の場合は・・・年相応 5~8の場合は・・・実年齢+10歳 9~12の場合は・・・実年齢+20歳
【血管事故の4大因子】 ①高血圧 ②脂質異常症 ③糖尿病 ④喫煙 これらは1つだけでも血管の老化を進行させますが、重なれば重なるほど血管の老化が加速していきます。例えば高血圧があると、血管事故を起こすリスクは健康な人の3倍です。そこに脂質異常症が加わると3×3=9倍さらに糖尿病も加われば3×3×3=27倍、喫煙もプラスされれば、なんと81倍にもリスクが跳ね上がります!逆に1つの因子を改善させれば、リスクもその分減りますので、早めに対策を講じましょうね!特に塩分の摂り過ぎとストレスには要注意ですよ・・・。
【血管が蘇る食生活】 ①血管若返りのための「やさいの法則」
・やさいを・・・野菜に含まれるファイトケミカル、ビタミンCなどが血管を若返らせる。 ・さきに・・・野菜の植物繊維が先に腸にあると、あとから入ってきた肉汁や脂肪の吸収を押さえられる ・いっぱい食べる・・・1日350gを目標に。生野菜だけでなく温野菜などでもOK 「やさいの法則」とは、食事の際は野菜を先にいっぱい食べるというシンプルな食事ルールです。野菜には、活性酸素から血管を守る抗酸化成分や、過剰なナトリウムを体外に排出するカリウムなど、血管の健康に役立つ成分が数多く含まれています。
②塩分の摂りすぎに気を付けましょう 塩分を摂りすぎると血圧が上がる理由は、喉が渇き、水を沢山飲むので血管内の水分が増え、血管を圧迫します。そして塩分に含まれるナトリウムが血管に入り込むと、血管がなめし革の様に硬く変化します。それによって塩分を排出させるため、腎臓から血圧を上げるホルモンが分泌される、という訳です。現在、日本人の食塩摂取量は成人男性で12g、成人女性で10gと、世界的に見ても高い水準です。これを徐々に下げ、6g以下を目標にすることを厚労省では唱っております。塩分の濃い味に慣れてしまった舌を、いきなり完璧を目指そうとしても難しいので、先ずは「塩8分目」を目標にして下さい。塩については次年度一度このくるくる保健室で取り上げたいと考えておりますので、乞うご期待下さいませ!
③嫌いなものは無理して食べなくていいよ! 血管の若返りのためとはいえ、嫌いなものを嫌々食べると、それがストレスになります。ストレスを感じると交感神経が優位になり、血管が収縮し、血圧も上昇します。それにより、かえって血管の老化を招くことになります。せっかくの食事は、自分が好きなものを、美味しいと思いながら食べるといいでしょう。すると、副交感神経が優位になり、血管が拡張し、血圧が下がって血管の若返りにつながります。自分が食べたいものを食べて下さいね!
④食べ過ぎだけには気を付けて 炭水化物、タンパク質、脂質のどれもが原料となり、肝臓でコレステロールが作り出されています。つまり、血管を傷つける悪玉コレステロールは、食事の総カロリーによって影響されています。食べ過ぎると総摂取カロリーが上がり、悪玉コレステロールの生産量も増えます。日常の食事では「腹8分」の厳守が大切ですが、結婚式、記念日、忘年会などの「ハレの日」には、我慢せずに好きなものを思い切って食べてもOKです。翌日からまた元に戻せばいいのです。
⑤1日2個の卵で良質なたんぱく質を補給しましょう 日本人の食事摂取基準2015年版でコレステロールの目標量が撤廃されました。これは、食品で摂取するコレステロール量が、直接血中総コレステロール値に反映することはないと分かったからです。コレステロール値を上げる、と敬遠されてきた卵も、卵の摂取量と虚血性心疾患や脳卒中による死亡率との関連はないことも分かりました。卵は、良質なたんぱく質をはじめ、ビタミン類、ミネラル類が豊富ですので、1日2個程度食べ、必要な栄養素をカバーしてみて下さい。
⑥植物繊維で血管掃除 植物繊維は食後の血糖値の上昇を抑える働きがあります。それだけではなく、血管を掃除するのにも役立ちます。水に溶けるりんご、こんにゃく、海藻類、モロヘイヤ等の水溶性食物繊維は、胆汁液の排出を促すことで血液中の余分なコレステロールを低下させる作用があります。水に溶けないごぼう、豆類、きのこ類等の不溶性食物繊維も便通を良くして害になるものを体外に排出し、血管を守る働きがあります。
⑦血管壁を丈夫にする亜鉛、セレンを積極的に摂りましょう インスリンは肝臓で合成されるホルモンの一種で、ブドウ糖の排出を促し、脂肪細胞をエネルギーに変換するなどの作用があります。インスリンにより体内の血糖値が保たれていなければ血糖値が上昇し、糖尿病などの病気に罹ります。そのインスリンを作り出しているのが亜鉛です。亜鉛不足になると必然的にインスリンが不足し、高血糖のリスクがあります。また、セレンも細胞の酸化を防ぐ働きがあり、血管の老化を防ぐのに欠かせないミネラルです。 亜鉛を多く含む食べ物・・・牡蠣・かに、豚レバー・牛ロース・チーズ・ごま・アーモンド・のり等 セレンを多く含む食べ物・・・かつお・まぐろ・たまご・カシューナッツ等
⑧マグネシウムで血管いきいき 血圧と血糖値の安定に不可欠なマグネシウム。マグネシウムには、血管の緊張を緩めて血流を改善し、血圧を正常に保つ働きがあります。また神経の興奮を鎮める働きもあり、血糖値が高い状態を改善し、糖尿病のコントロールにも効果があると言われています。また、最近の研究では骨粗鬆症等の骨に関する病気にも、カルシウムと共にマグネシウムの摂取が大切であると言われております。 加工食品やインスタント食品、清涼飲料水には、マグネシウムの吸収を阻害するリンという成分が含まれています。これらの食品を多く摂る人は、マグネシウム不足になりやすい傾向になります。また、飲酒量が多い人もマグネシウム不足になりやすいので、ほどほどにね! マグネシウムの多い食べ物・・・豆腐・貝類・とうもろこし・ナッツ類等
⑨血管を若返らせるよい脂α-リノレン酸(オメガ3) 青魚に多く含まれるEPAやDHA、えごま油、亜麻仁油は、必須脂肪酸の一種で血小板の凝集を防いで血流を良くしたり、余分なコレステロールや中性脂肪の代謝を促進する作用があります。さらに傷ついた血管の機能を回復し、柔らかくしなやかな血管の状態に戻すともいわれております。さばの水煮缶がいいですね!
⑩大豆で悪玉コレステロールを撃退 畑の肉とも言われる大豆は血管の老化を防ぎます。大豆たんぱくは、悪玉コレステロールの酸化を防ぎ、胆汁酸とともに悪玉コレステロールを絡め取って便として出し、血圧を上げるホルモンを作る働きにブレーキをかけて血圧を安定させる作用があります。しかも、悪玉コレステロールが多い状態であればあるほど、その働きが増すと言われています。昔ながらの和食の力を見直し、もっと食卓に登場させたいものですね!
⑪ファイトケミカルが血管を酸化から守る フランス人はチーズやバターなどの乳脂肪や、フォアグラや肉類などの動物性脂肪の摂取量が多いにもかかわらず、動脈硬化患者が少なく、狭心症や心筋梗塞による死亡率も低いことが知られています。この現象を「フレンチパラドックス」といいます。 その秘密は、フランス人が日常的に飲んでいる赤ワインに含まれるレスベラトロールという「ポリフェノール」にありました。ポリフェノールとは、植物の樹皮や表皮、種子などに含まれる色素成分や苦味・渋味成分のこと。強力な抗酸化作用があり、レスベラトロールも血管を酸化から守っていると考えられるのです。ポリフェノールの様に、植物性食品に含まれる化学物質を「ファイトケミカル」といい、人間の健康に役立つものがたくさんあります。 一方、コーヒー大国・アメリカにちなんだ「アメリカンパラドックス」もあります。コーヒーに含まれるクロロゲン酸というポリフェノールには抗酸化作用があり、血液をサラサラに保つ効果があると言われています。最近、コーヒーを習慣的に飲むことが動脈硬化による心筋梗塞などの予防に効果的であるという研究成果が相次いで報告され、心筋梗塞の再発を防止するアスピリンという薬よりもコーヒーの効き目の方が強かったとの報告も。1日に3~4杯程度、ブラックの浅煎りで飲むのがお薦めです。コーヒーもお酒も依存症になりますので飲み過ぎには気を付けましょうね!
【血管若返りの天然の薬“一酸化窒素”(NO)の増やし方】 血管の老い、すなわち動脈硬化は、血管内皮細胞が傷つけられることから始まります。この血管内皮細胞をケアしてくれるのが、一酸化窒素(NO)という物質です。NOには、血管を広げて血流を促したり、血管壁の傷を修復したり、血栓をできにくくする、といった働きがあります。まさに、血管にとって天然の薬なのです。NOを分泌しているのは、実は、血管内皮細胞です。ですから、内皮細胞が傷つくとNOの分泌が減り、さらに内皮細胞のダメージが進む、という悪循環に陥ってしまいます。この悪循環を断ち切るには、食生活の改善が欠かせません。食生活を改善することで、内皮細胞へのダメージを減らし、NOが働きやすい体をつくることができます。 食生活は前述した内容をご参考にして下さい。それにプラスしてNOを増やす食材としてもう一品ご紹介させて下さい。それは皮をむいた玉ねぎを一週間干したものです。元々玉ねぎには体内に発生した活性酸素を抑え内皮細胞の老化を防いで、血管を開いて血圧を下げる働きがあると言われる「ケルセチン」というポリフェノールの一種が多く含まれております。ただ問題なのがケルセチンは玉ねぎの皮に多く、その皮は普通は、むいて調理してしまいますが、日の当たる窓際や籠に入れベランダにぶら下げ日光に当てる事によって干し玉ねぎにすると通常の4倍もののケルセチンが出来ます。また、玉ねぎには食物繊維やオリゴ糖など、腸内環境を整える成分も多く含まれアレルギー疾患にも効果があると言われるのも大変魅力的な食材ですね! 以下、NOを増やし血管を若返りさせる運動のやり方とちょっとした工夫をしただけで血管が若返る生活術を最後にご紹介したいと想います。
【血管若返り簡単体操】 ①週2回の20分早歩き
今まで運動の習慣が無かった人は、週2回、20分位のウォーキングからスタートしてみて下さい。正確な時間にこだわり過ぎるとかえって緊張して血管に良くないのでだいたい20分位で歩けるコースを3コース位あらかじめ決めておき、自分の急ぎ足位のスピードで歩くと良いでしょう。 この早歩きウォーキングによって、血管の内皮細胞で「プラジキニン」という生理活性物質が分泌されると、血管内で一酸化窒素が刺激され、その作用で血管が拡張します。また、ふくらはぎを中心とした筋肉の収縮によって下半身の血液が心臓に押し戻される「ミルキングアクション」が起こり、血液の循環が良くなります。さらに、ウォーキングをすると交感神経が優位になり、内臓脂肪の分解を促進するアドレナリンというホルモンが分泌されます。お薦めの時間は交感神経から副交感神経優位になる夕方がベターです。この時間帯は適度に血圧が上がっているので心臓に負担をかけませんし、帰宅時間帯を利用しウォーキングが出来るからです。 尚、雨が降っている時は歩かなくてOKです。雨で体が濡れると、血管が縮んで血圧が上がります。た、気温が低いので余計に血圧が上がりやすくなります。雨の日は無理せず自宅内でつま先立ちポンプアップや座ったまま(長座)で足関節部を前後に倒したりすると、ふくらはぎを刺激して血管も若返りますよ!今週は2回しか歩いてないから、今日は雨だけど歩こう等とは決して想わないでくださいね、歩けないときは「しょうがない」位の気持ちで想っててください。
②ももたろう体操(ゾンビ体操) 加圧トレーニングが一時大ブームになりましたが、血管を駆血することにより腕や脚を一時的に低酸素状態にすることで、脳に信号が送られ、低酸素になっている腕や脚を修復させるための各種ホルモンや血管内皮が刺激されて一酸化窒素が分泌される、と言われております。それが他の部位にも働き、かえって心筋梗塞などの血流の悪い所が改善したりすると言われています。5分以内の駆血は安全ですし、骨折や捻挫、肉離れ等のケガにも効果があったり、神経痛やしびれが改善したり、肩こりや筋肉痛が改善したり、全身の血流が良くなることで冷え症の改善に繋がったり、脳の血流も良くなって歩行姿勢が安定したり等の効果があります。 ここで言う駆血とは止血法の一種で虚血法ともよび、四肢の外傷や下腹部や下肢の大量出血の際などに強靭なゴム管で動脈壁を完全に圧迫する強さで四肢あるいは腹部を緊縛し、血液の喪失を防ぎ止血を行う事を言います。 このメカニズムを利用して布団やベットの上で風呂上がりに仰向けの姿勢で両膝を抱え込んでグーッと力を入れて丸くなり、血管を30秒~1分間位キープし圧迫してから、一気に身体の力を抜いて脱力し大の字になって、手と足をゆすってブラブラっと揺らすと血流がよくなって深部体温が程よく下がり、ぐっすりと寝られます。これを就寝前に1~3回行うと効果的です。
運動は行うタイミング次第で毒にもなるし薬にもなります。お薦めのタイミングは食後30分です。なぜなら、食事の30分後からは血糖値が上がり始めるので、そのタイミングに身体を動かすと、糖の吸収が抑えられ、血糖値の急上昇を防げます。逆に起床後の朝は激しい運動は危険です!朝は誰でも血圧が高めで、就寝中に水分が失われて血液の粘り気が強い為、血管が詰まりやすく血管事故の原因になります。朝運動する場合は運動前に水分を補給し軽いウォーキング程度にとどめるのが賢明です。
『その他の血管若返り養生法』
①血管若返り呼吸法 自律神経を自分の意志で自由にコントロール出来る唯一無二 の方法が呼吸です。 ゆっくりとした深い呼吸をすることで体がリラックスモードに入って副交感神経が優位になります。それによって血管も柔らかく緩んで血圧も低下して行き、結果的に血管もリラックスして若返って行きます。以前のくるくる保健室の記事でも何度か書いておりますが5秒息を吸い、5秒間止めて、10秒間吐く1:1:2の呼吸法がいいと想います。 また、息を吐き切ってから、お腹と背中をくっつけるようなイメージで、お腹を凹ませ、お腹に力を入れたまま呼吸を続けるドローインをすることで、インナーマッスルの腹横筋が鍛えられ、姿勢が良くなって若々しく見えたり、胃腸の働きも活発になります。有酸素運動と筋トレが同時に出来るドローインは一酸化窒素の分泌も増えて血管が若返ります。色々な生活のシチュエーション場面で歩きながらでも、駅のホームで電車を待っている時でも、自宅のソファーでくつろいでいても、キッチンで料理を作りながらでも手軽に出来て便利です。
②血管若返り睡眠法
睡眠は、血管を修復するための大切な時間です。ポイントは毎日同じ時間に起きる事と量より質です。良質な睡眠は血管の健康維持に欠かせません!その理由は3つあります。 1つは、睡眠中に分泌される成長ホルモンが血管の傷を修復してくれること。2つめは、睡眠中に分泌されるホルモンの一種メラトニンが、高血糖を防ぎ2型糖尿病を予防してくれること。3つめは、睡眠中は副交感神経が優位になり、血圧や心拍数が下がること。日中に比べて、血管や心臓にかかる負担が軽くなります。 睡眠時間は6~8時間が理想とされていますが、個人差がありますし、何時間寝たかよりも、ぐっすり寝れたと感じる事が大切です。
③血管若返り入浴法 ヒートショックでの入浴中の突然死は12~1月がピークです。冬場の脱衣場の温度は大体10℃、衣服を脱いで浴室に入ると8℃、寒くて血管が収縮し、血圧が上昇します。湯につかった瞬間にさらに血管が縮んで血圧が上昇し、その後血管が拡張して血圧の急降下が発生、血管事故が起こります。ですから先ず入浴前に浴槽のフタを空け、湯気を出し浴室を温めておく事と、脱衣場は暖房器具を入れて予め温めておくという準備をしてから入浴されるといいです。始めに湯に入る時は「あ~」とか声を出す事で力まず脱力すると交感神経を緊張させずに済みますし、手足をグーパーさせ更に血流をアップさせて、41℃以下のぬるめの湯に5~15分長くても20分以内で切り上げる事。熱い湯に長くつかっていると汗をかいて脱水状態になり血液がドロドロしますので、入浴の前後にはコップ一杯の水を飲むといいです。半身浴もいいのですが、冬場は風邪の原因になりますので控えたほうが無難です。
④血管若返り歯みがき 歯周病と血管は何の関係もなさそうですが、実は非常に深い関係にありました。歯周病は、喫煙、高血圧、高血糖、脂質異常、内臓脂肪型肥満と同様に動脈硬化を進める事が判明いたしました。 歯周病とは、歯と歯ぐきのすきまに歯周病菌が増殖してプラーク(歯垢)をつくり、歯肉に炎症が起こる病気です。進行すると、歯を支えている組織が溶けて、歯が抜けてしまう事もあります。これがなぜに動脈硬化を引き起こすかというと、歯の周囲の毛細血管から歯周病菌が血管内に入り込み、血管内膜に炎症を起こすからではないかと考えられています。 30歳以上の日本人の8割は歯周病といわれているので、他人事ではありません。毎日の歯みがきで歯周病を予防することが重要です。また、半年に一度は歯みがきでは落としきれない歯石を歯科医院で除去してもらうのが理想的です。
⑤高血圧の人も汗をかいたら水と塩を摂取 血管の老化を防ぐには減塩することが基本ですが、その一方でナトリウムは体にはなくてはならない必須ミルラルのひとつです。一日に最低限必要な摂取量は1.5g程度。真夏に運動をして大量に汗をかいた時には、水分だけではなく、必要なナトリウムも失われていますので汗をかいたら、高血圧の人でも塩分の補給が必要です。水ではなくスポーツドリンクや経口補水液を摂取し熱中症を予防しましょう。 ⑥電話は3回鳴ってから出る 家で電話が鳴って、慌てて受話器を取ろうとするようなせっかちな性格は、血管にとってはよくありません。「すぐに出なければ」という気持ちがストレスになり、血管を縮めてしまうからです。本人は、自分の性格が血管や心臓によくないということに気付いていません。電話が鳴ったら、「ああ電話か。仕方がない。出てやろう」くらいの気持ちで、3つ数えてから受話器を取るくらいで丁度いいのです。3回目で出ても、相手は「遅い」とは思いません。
⑦泣いて笑ってストレス発散 大人になると、人目を気にして泣いたり笑ったりするのを我慢してしまいますが、この時血管にも我慢を強いています。泣くのを我慢していると、ストレスで交感神経が緊張し、血管を縮めます。泣きたいときは、血管の為にも、ためらわず泣いてしまいましょう。涙の中には脳から分泌されるプロラクチン、コルチゾール、ACTHといったストレスの原因となるホルモンが含まれており、涙とともに排出されます。すると、泣いた後は心身がリラックスし、副交感神経が優位になって血管が広がり血圧も下がります。 一方、笑いも血管の若返りに有効です。笑うと副交感神経が活性化し、体の緊張が解けてリラックスします。それによって血管が拡張し、血圧が下がり、動脈硬化による血管事故も防げます。また、笑うと脳内にβ-エンドルフィンという物質が増えます。β-エンドルフィンは脳に快楽をもたらす物質で、心身の緊張を解きます。この作用によっても血管が拡張します。笑いは脳の前頭葉という部分を興奮させ、その興奮が間脳に伝わると快い感情を伝える神経ペプチドがつくられ、全身にふりまかれると、心身がリラックスし、血管を開いて血圧を下げてくれます。このように、笑いや涙でストレスを発散させると、血管もリラックスし、血管事故の予防になります。
⑧怒らない、こだわらない。「まぁいいか」が大切 怒ると血圧が上がるという言葉の通り、怒りは交感神経を優位にし、血管を収縮させて血圧を上昇させます。実際に怒りっぽい人は、心筋梗塞などの血管事故を起こしやすい傾向も。また、こだわりや執着があるとストレスになり、血管によくありません。「まぁいいか」と大目に見る器を持ち血圧上昇を予防しましょう。もし、怒られた時も、いちいちビクッと緊張していると、血管が収縮してしまいます。相手が怒っている内容にもよりますが、「すみません」と受け流し、嵐が去るのを待つのが血管を傷つけないコツです。 「まぁいいか」の5か条 1.怒られても受け流す 2.明日やればいいことは、今日やらない 3.使わないものは捨てる 4.いい人になりすぎない 5.家庭円満を心掛ける
⑨年に一度は健康診断を受けよう 40歳を過ぎると、血管の老化=動脈硬化が加速するようになります。年1回の健康診断を必ず受け、動脈硬化のリスクファクターである高血圧、糖尿病、脂質異常症のシグナルを早めにキャッチするようにしましょう。早く見つけて治療するほど、改善効果が高まります。ACジャパンのコマーシャルは川中島の合戦を再現してコミカルに上杉謙信と武田信玄のかけあいを心臓弁膜症へと誘い息切れは心不全の原因となる弁膜症のサインかもと「高齢者には進言(信玄)を!」「早めに検診(謙信)を!」と流しております。なかなかのインパクトがありましたよね! 血管の状態を調べる検査 1.頸動脈エコー検査 首から脳につながる頚動脈に傷やコブがないか調べる。脳卒中の危険度もわかる。 比較的小規模な医療機関でも受けられ料金は7000円前後 2.血管内皮機能検査
血管を守る一酸化窒素が血管内皮からどのくらい分泌されているかを調べる。 脳ドックや心臓ドックを行っている医療機関で、3500円前後 3.脈波伝播速度検査・加速度脈波検査 血管全体の状態を調べ血管のしなやかさを調べる。 人間ドック等を行っている医療機関で2500円前後 4.血液検査・血圧検査 血管の老化を進める4大リスクファクターの内の3つの有無を調べる。 高血圧・高血糖・脂質異常の有無、境界型の人も要注意! 5.アキレス腱の太さを測って家族性高コレステロール血症を予防するセルフチェック 日本に30~60万人いると言われる生まれつきコレステロール値が高い家族性高コレステロール血症の方は血管事故のリスクが13倍と高く、LDLコレステロール値が180以上、2親等以内の家族が狭心症や心筋梗塞を患った経験がある、男性55歳未満女性65歳未満でアキレス腱の太さは通常だと6mm程度ですが、2㎝以上になっているとこの家族性コレステロール血症を患っている可能性があると言われております。
胸が15分以上押される痛みが続いたり、強い不安感に襲われたり、冷や汗や吐き気、息苦しさを伴う時にはすぐに病院に行きましょうね!
【家族を救う魔法の呪文】
最後になりますが、もしも目の前で大切な人が突然倒れてしまったらどうしますか? そんな時我々が出来る救命方法が心臓マッサージです。ここではやり方のポイントをご説明いたします。 心臓マッサージ(胸骨圧迫)は実は心臓を復活させるために行うのではなく脳などの重要な臓器へ血液を送る事が一番の目的です。つい胸を強く押せばいいのだろうと想うかもしれませんが、押すだけではなくしっかりと「引く」事が大事です。「引く」動作が弱いと血液が心臓に十分に戻らないために、脳にも血液を少ししか送り出せないのです。とは云え、実際現場を目の当りにすると慄いたり恐れたりしてしまうとは想いますが、ここは勇気を振り絞って、ある医師が考案したプリンセスプリンセス(赤坂小町)の大ヒット曲「ダイヤモンド」に合わせて行う方法。曲の拍子のあいだに入る裏打ちのリズムがはっきりとした曲なので、押す動作とともに、「引く」動作もしっかり意識でき、しかも曲のリズムが心臓マッサージに理想的な1分間に100~120回の拍数とぴったりで、もし突然人が倒れたら、心の中でこの曲を歌い、是非とも勇気を出して心臓マッサージを行って下さい。♪冷たい泉に素足をひたして 見上げるスカイクレイパー 好きな服を着てるだけ 悪いことはしてないよ・・・♪ときっと曲が気持ちを後押ししてくれるはずです。また、AEDが近くにある場合は、併せて使用して下さい。
※心停止して4~5分経過すると、脳が助からない可能性が高くなります。呼吸をしてなかったら心臓マッサージを始めて下さい。 ①救急車を呼ぶ ②心臓マッサージを開始する。 ③もう一人いればAEDを持ってきてもらう。そしてAEDの音声に従って操作し必要な場合は電気ショックを行う。 ④AEDが終わったら、心臓マッサージを再開。
自宅で練習する場合・・・ タオルで包んだ、側面が平らな2リットルのペットボトルや座布団を4枚重ね一番上の1枚は半分に折ってその上から心臓マッサージの練習をするといいです。最近は一般の方は人工呼吸をする必要はなく、練習は生のヒトには危険ですので絶対に行わないで下さい。
かわい接骨院・じょんのびはり・きゅう治療室 手技療法家 川合 晃生




Comments